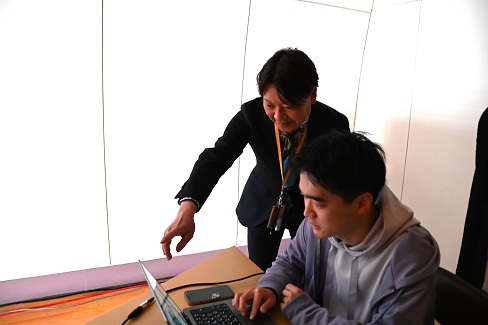経営学部が改組され、新しく誕生した「コミュニケーション・デザイン学科」の学科長に就任した谷口准教授。卒業式、入学式に新学科の発足準備も重なった多忙な時間の合間を縫って、新学科に対する抱負などをうかがいました。
――新しい学科ができました。
前身の東邦学園短大には商業デザインコースがありましたが、20年ほどでなくなりました。コミュニケーション・デザイン学科は、今の時代に合う形での数十年ぶりの復活だと思うので、感慨深いものがあります。
新学科では映像制作とかイベント演出などライブ型の授業を行います。ブランド、マーケティング、広報宣伝といった分野で、グラフィックデザインや映像などを使って、初見での好印象を消費者に与えることができるということを学べます。より良いアイデアをより良く伝える、クリエイティブの力でビジネスを加速させることができると思っています。プレゼンテーション能⼒も⾝につきます。
――どんな学生を育てていきたいですか?
デザインとか芸術で食っていくというのは、かなり覚悟が必要です。でもクリエイティブなことも学びたいと思っている人にとっては、新学科は経営学部なので「ビジネス」が担保されているわけです。ビジネスにプラス表現スキルを学べるわけですから、就職してもすぐに役立ちますよ。でも私が考えているのは、企業から独立しても腕一本でやっていける人材の育成です。つまり「社会で生き抜く力を持った強い人材」を育てたいですね。
――もともと先生のゼミは「スキルの実装」を掲げ、テクニカルなことも教えていますね。
2012年に共同で映像デザインを中心とした会社組織デンキトンボを立ち上げ、今でも取締役を務めています。小さな会社ですので私自身も経営から現場作業まで何でもこなさなければいけません。専門的な機材を使ってテクニックを教える際には、基本的なことをやってみせると、学生たちも若い感性ですぐに適応していきます。映像とかグラフィックデザインとか、自分の「売り」のスキルを身に付けられます。今年卒業したゼミ生の一人が、内定した企業の新商品のポスターデザインを作成し、卒業研究の一環でその企業に売り込み、社内評価までいただきました。うれしい成果でした。積極性が出てきたな、と思いました。これはまさに生き抜いていく力だと思います。そんな学生たちに期待しています。
――しかし、誰もが絵やデザインが得意なわけではないですよね?
実は私自身、高校までは絵が苦手だったんですよ。面白さも分かりませんでした。理系でしたので、このまま理工学系の大学に進むんだろうなとぼんやり考えていました。ところが1989年に名古屋で開かれた「世界デザイン博覧会」でメディアアートに出合ったんです。衝撃的でした。コンピューターグラフィックスのキラキラした映像を見て、「これをやってみたい」と進路がはっきりしました。その出展者が教員をしていた神戸芸術工科大学を進学先に選びました。でも大学では絵やデッサンがうまい人ばかりで、ついていけるのか、やっていけるのか戸惑いました。だから、今も私のゼミには絵が苦手な人もいるのですが、そんな不安に寄り添うように指導方法を考えたりしています。
――教員になったのはなぜですか?
大学1年の冬、一番大きな出来事が起きます。阪神淡路大震災です。神戸市の西部に住んでいたんですが、暮らしていたアパートや周辺地域、同級生や知り合いも多くの被害を受けていました。短期間でしたが避難生活も経験しました。価値観がガラガラと変わりました。日常の中でも常に何か起きるんじゃないかという意識が芽生えました。そして、これから復興していくこの地域(神戸)で、専門分野を活かしていこうと決心しました。それ以来、関西を中心に活動しています。カーナビのシステムを開発している会社に入って、CG技術を磨きました。その会社の系列の専門学校に講師として出向し、そこから教育の道に入りました。京都造形芸術大学(今の京都芸術大学)で専任講師となり、その後2012年に仲間と会社を作りました。イルミネーションとプロジェクションマッピングの会社で、これが先ほども話しましたデンキトンボです。
――本学のイベントではよく演出の裏方を務めていますね。
本学に着任した時、ビジネス中心の経営学部の中でどうしたら自分の専門を生かせるか、戸惑っていたというのが正直なところです。ただコロナ禍の真っただ中で、リモートワーク、ビデオ会議の時代でした。どちらも専門分野だったので、さっそくノウハウを提供して少しだけ居場所ができました。イベントの演出は苦でも何でもありません。去年と今年の卒業式では、学生たちがマーチングバンドの音に反応する照明を演出しました。今年の入学式の演出もほぼ学生任せでした。
――「常に違う景色を視ている」というのが先生のクレドですね。
私はいつも物事の見方を変えることを心がけています。学生には、新しいことをやっても、他人と違っていても大丈夫だよ、と言ってあげたい。地元愛が強いのか、居心地がいいのか、積極的に「外」に出たがらない学生が多いですね。「外」には面白いことも多いのに、出て行かないのはもどかしいです。本学の学生には、そこを打ち破ってほしいと思っています。